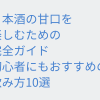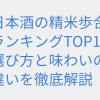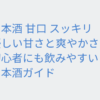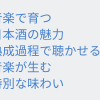日本酒 中取りとは|製法・特徴・味わい・選び方まで徹底解説
日本酒には「あらばしり」「中取り」「責め」といった搾り方による分類があり、その中でも「中取り」は特に品質が高いとされています。本記事では「中取り」の意味や製法、味わいの特徴、他の搾り方との違い、そして選び方や楽しみ方まで詳しく解説します。日本酒選びの幅を広げたい方や、贈り物に迷っている方にも役立つ内容です。
1. 日本酒の「中取り」とは
- 中取りの定義と搾り工程での位置
日本酒の「中取り(なかどり)」とは、もろみを搾る工程の中で、最もバランスが良く品質が高いとされる部分を指します。日本酒造りでは、発酵させたもろみを「搾り(上槽)」の工程で酒袋や機械にかけて日本酒と酒粕に分けます。この搾りのタイミングによって「あらばしり」「中取り」「責め」という名称が付きます。
まず、圧力をかける前に自然に流れ出てくるお酒が「あらばしり」。その後、適度な圧力をかけて搾り出される中間層が「中取り」と呼ばれます。この「中取り」は搾りの中でもっとも透明感があり、雑味が少なく、香りと味のバランスが取れているのが特徴です。最後に、さらに強い圧力をかけて搾り切った部分が「責め」となります。
「中取り」は「中垂れ」や「中汲み」とも呼ばれ、蔵元によって表記が異なることもあります。この部分は日本酒の中でも特に品質が高いとされ、品評会や贈答用にも選ばれることが多いです。市販の日本酒では、通常これら3つの部分をブレンドして出荷することが多いですが、最近は「中取り」だけを瓶詰めした限定品も増えています。
「中取り」を知ることで、日本酒の奥深い味わいや造り手のこだわりをより感じられるようになります。ラベルで「中取り」と見かけたら、ぜひ一度その特別な味わいを楽しんでみてください。
2. 「あらばしり」「中取り」「責め」の違い
- それぞれの搾り方と味わいの違い
日本酒の「あらばしり」「中取り」「責め」は、もろみを搾る工程で採れるタイミングによって分けられる呼び名です。それぞれの部分には、味わいや香り、酒質に個性があり、同じ仕込みタンクでもまったく異なる表情を見せてくれます。
まず「あらばしり」は、搾り始めて最初に自然と流れ出てくる部分です。オリと呼ばれる細かな酒粕が含まれているため、やや濁っていることが多く、フレッシュで若々しい香りやピチピチとした微発泡感が楽しめます。香りが華やかで、ワイルドな味わいが特徴です。
次に「中取り」は、あらばしりの後、適度な圧力をかけて搾り出される中間部分です。透明で雑味が少なく、味と香りのバランスに優れ、まろやかで落ち着いた飲み口が魅力です。品質が安定しているため、品評会や贈答用の日本酒にもよく選ばれます。
最後の「責め」は、さらに強い圧力をかけて搾り切った部分で、アルコール度数がやや高く、味わいは濃醇で雑味が感じられることもあります。荒々しさや力強さが特徴で、個性的な味を好む方には魅力的な部分です。
このように、搾りのタイミングによって日本酒はまったく違う個性を持ちます。ラベルに「あらばしり」や「中取り」と記されているときは、その特別な味わいをぜひ意識して楽しんでみてください。
3. 中取りが「最高品質」とされる理由
日本酒の「中取り」は、搾り工程の中盤で得られるお酒で、もっとも品質が高いとされています。その理由は、まず雑味が少なく、香りと味わいのバランスが抜群であることです。搾り始めの「あらばしり」はフレッシュで力強い反面、やや荒々しさや不安定さが残り、搾り終盤の「責め」は圧力を強くかけるため雑味や濃厚さが強く出ますが、「中取り」はその中間にあたり、透明感のあるクリアな味わいと、まろやかで落ち着いた口当たりが特徴です。
この部分は日本酒の“おいしいところ”とも呼ばれ、蔵元や品評会でも重宝されています。実際に品評会に出品される日本酒の多くは「中取り」が選ばれるほど、その品質の高さが認められています。また、芳醇でエレガントな香りや、飲みやすさも「中取り」ならではの魅力です。
最近では、この「中取り」だけを瓶詰めした限定品も多く登場しており、贈答用や特別な日の乾杯にも選ばれることが増えています1。透明感・バランス・まろやかさ――これらが揃った「中取り」は、日本酒の魅力を存分に味わいたい方にぜひおすすめしたい最高品質の一杯です。
4. 中取りの呼び名と表記
日本酒の「中取り」は、搾り工程の中間部分で得られるお酒ですが、蔵元や地域によって呼び名やラベル表記が異なることがあります。代表的な別名として「中垂れ(なかだれ)」「中汲み(なかぐみ)」があり、これらはすべて同じ“中間層”で搾られる高品質な部分を指します。
ラベルには「中取り」「中垂れ」「中汲み」といった表記がされていることが多く、いずれも味と香りのバランスが良く、雑味が少ないお酒であることを意味しています。また、同じ「中取り」でも、搾りの工程や圧力のかけ方によって、さらに細かく分けられる場合もあり、蔵元によっては自重のみで流れ出たものと、軽く圧力をかけて出てきたものを分けて表記することもあります。
このようなラベル表記を知っておくと、日本酒売り場や飲食店で自分の好みに合ったお酒を選びやすくなります。「中取り」や「中垂れ」「中汲み」と書かれた日本酒は、まろやかで透明感のある味わいが特徴なので、贈り物や特別な日の一杯にもおすすめです。ラベルの呼び名に注目して、日本酒選びをより楽しんでみてください。
5. 中取りの製法と工程
日本酒の「中取り」は、発酵が終わったもろみを搾る工程の中で、最もバランスが良く高品質な部分を指します。伝統的な「槽搾り(ふねしぼり)」では、発酵させたもろみを酒袋に詰めて槽(ふね)に並べ、上からじっくりと圧力をかけて搾っていきます。このとき、圧力をかける前に自然と流れ出る部分が「あらばしり」、その後、適度な圧力をかけて搾り出される中間部分が「中取り」、さらに強い圧力で最後まで搾った部分が「責め」と呼ばれます。
「中取り」は、搾りの途中で得られるお酒で、透明感があり、香味のバランスが非常に優れています。現代では「ヤブタ式」と呼ばれる機械搾りも主流ですが、機械でも同様に「あらばしり」「中取り」「責め」と分けて管理されることが多いです。
また、大吟醸酒などの高級酒では、酒袋を吊るして自然に滴り落ちる雫だけを集める「袋搾り」や「しずく取り」といった手間のかかる方法が用いられることもあります5。このような方法で搾られた「中取り」は、特に香り高く、雑味が少ない上質な日本酒として重宝されています。
搾り方や圧力のかけ方によって、同じもろみからでも味わいや香りが大きく変わるのが日本酒の奥深さです。「中取り」は、まろやかで透明感のある味わいを楽しみたい方におすすめの製法です。
6. 中取りの味や香りの特徴
- 雑味の少なさ、香味のバランス、飲みやすさ
中取りの日本酒は、搾り工程の中間部分で得られるため、非常に透明感があり、雑味が少ないのが大きな特徴です。味わいはとてもまろやかで、香りと味のバランスが優れており、落ち着いた印象を与えてくれます。たとえば、「洋ナシのようなフルーティな香り」や「しっかりとした味わい」が感じられることもあり、飲みやすさと上品さを兼ね備えています。
中取りは、あらばしりのフレッシュで荒々しい個性や、責めの濃厚で複雑な味わいとは異なり、全体的にクリアで安定した酒質が楽しめます。そのため、日本酒の品評会や贈答用としてもよく選ばれており、「もっとも質の良い部分」として評価されています。
また、雑味が少なく、香りと味のバランスが取れているので、日本酒初心者の方にもおすすめです。飲みやすく、食事とも合わせやすいので、ぜひ一度中取りの日本酒を味わってみてください。きっと日本酒の新たな魅力に気づくはずです。
7. 中取りが使われる日本酒の種類
- 鑑評会用や限定品、贈答用の中取り酒
中取りは日本酒の搾り工程で最も品質が高いとされる部分であり、そのため特別な日本酒に多く使われています。たとえば、酒蔵が自信を持って出品する「鑑評会用」の日本酒や、蔵元限定の特別な一本、贈答用としても人気の高い日本酒が中取りとして瓶詰めされることがよくあります。
中取りの日本酒は、雑味が少なく、香りと味のバランスが非常に良いのが特徴です。華やかな香りと、ふくらみのある優雅な味わいが楽しめるため、特別な日の乾杯やお祝い事、大切な方への贈り物にも最適です。また、最近では市販品でも「あらばしり」「責め」といった他の搾り部分とブレンドせず、中取りだけを瓶詰めした限定商品も増えてきました。
純米大吟醸や吟醸酒など、香り高く繊細なタイプの日本酒に中取りが選ばれることが多く、ラベルに「中取り」「中垂れ」「中汲み」と記載されている場合は、その品質の高さの証と言えるでしょう。特別な味わいを求める方や、日本酒好きの方へのプレゼントにもぴったりです。中取り酒を選ぶことで、日本酒の奥深い世界をより一層楽しむことができます。
8. 中取り日本酒の選び方
- ラベルの見方や選ぶポイント
中取り日本酒を選ぶ際は、まずラベルに注目しましょう。「中取り」「中汲み」「中垂れ」などと記載されているものは、搾り工程の中間部分だけを瓶詰めした特別な日本酒です。この部分は雑味が少なく、香りと味わいのバランスが取れているため、品評会や贈答用にも選ばれることが多いです。
また、ラベルには製法や原料米、精米歩合、アルコール度数なども記載されています。吟醸酒や純米大吟醸など、香り高く繊細なタイプの日本酒に「中取り」が使われていることが多いので、好みのタイプと合わせて選ぶのもおすすめです。
さらに、「中取り」と表記された日本酒は、丁寧に搾り分けている証拠でもあります。あらばしりや責めとブレンドせずに仕上げているため、よりクリアで安定した味わいが楽しめます。贈り物や特別な日の乾杯に選ぶのはもちろん、日本酒初心者の方にも飲みやすいので、初めての一本にもぴったりです。
ラベルの情報をよく見て、「中取り」表記のある日本酒を選ぶことで、ワンランク上の味わいと香りを堪能できます。自分の好みやシーンに合わせて、ぜひ中取り日本酒を選んでみてください。
9. 中取りのおすすめの飲み方
- 温度帯やグラス選び、料理との相性
中取り日本酒は、雑味が少なく香りと味わいのバランスに優れているため、その上質な特徴を活かす飲み方がおすすめです。まず温度帯については、冷やして飲むのがもっとも人気です。特に5〜15℃程度の冷酒は、透明感のある味わいとフルーティな香りが際立ち、熟した果実のような旨みや甘みが楽しめます。冷蔵庫でよく冷やしたり、氷水で瓶ごと冷やす方法も手軽です。
グラス選びも大切で、ワイングラスや口の広い酒器を使うと、香りがふんわりと広がりやすくなります。特に吟醸系の中取りは、華やかな香りを存分に楽しめるのでおすすめです。
また、アルコール度数が高い生原酒タイプの場合は、ロックで飲むと柔らかい甘さになり、後味もすっきりします。日本酒が強く感じられる方や暑い季節には、氷を入れて楽しむのも良いでしょう。
料理との相性も幅広く、繊細な和食はもちろん、チーズや白身魚のカルパッチョ、軽めの洋食とも好相性です。雑味が少なくまろやかな中取りは、素材の味を引き立てるので、食中酒としても活躍します。
さらに、飲みすぎを防ぐためにも「和らぎ水」を用意し、合間に水を飲みながらゆっくり味わうのもポイントです。
中取りの日本酒は、冷やして、香りを楽しみながら、いろいろな料理と合わせてみてください。きっと新しい日本酒の魅力に出会えるはずです。
10. 中取りの魅力を最大限に楽しむコツ
- 保存方法や開封後の楽しみ方
中取りの日本酒は、雑味が少なく繊細な味わいが魅力なので、保存方法にも少し気を配るだけで、より美味しく楽しむことができます。まず、購入したら直射日光や高温を避け、冷暗所で立てて保存するのが基本です。特に「生酒」や「吟醸酒」「大吟醸酒」などはデリケートなため、冷蔵庫での保存が推奨されます。瓶を立てて保管することで、空気との接触面を最小限にし、酸化や劣化を防ぐことができます。
開封後は、できるだけ早めに飲み切るのが理想です。特に風味や香りを大切にしたい中取り酒は、開けたてのフレッシュさを3~5日以内に味わうのがおすすめです。もし飲み切れない場合も、冷蔵庫で保存し、1週間以内を目安に楽しみましょう。
さらに、瓶ごと新聞紙などで包んでおくと、急な温度変化や光からも守ることができ、品質を長持ちさせることができます。もし風味が落ちてしまった場合は、料理酒として活用するのも一つの方法です。
中取り日本酒は、その繊細な香りや味わいを存分に楽しむためにも、正しい保存と早めの飲み切りを心がけてください。大切な一杯を、最後まで美味しく味わいましょう。
11. 中取りと他の搾り方の飲み比べ
- あらばしり・責めとの違いを体感する楽しみ
日本酒の「あらばしり」「中取り」「責め」は、同じ仕込みタンクから搾り出されるお酒でも、搾るタイミングによって味わいや香りが大きく異なります。飲み比べをすることで、その違いを実際に体感でき、日本酒の奥深さや造り手の工夫をより感じられるでしょう。
まず「あらばしり」は、搾りの最初に自然に流れ出てくる部分で、やや白濁していることが多く、フレッシュで華やかな香りとピチピチとしたガス感が特徴です。若々しく力強い味わいが楽しめます。
「中取り」は、搾りの中盤で得られる透明で澄んだお酒で、雑味が少なく、香りと味わいのバランスがもっとも良い部分です。まろやかで落ち着いた飲み口があり、飲み比べの中でも一番安定した味わいを感じられるでしょう。
「責め」は、搾りの終盤に強い圧力をかけて得られるお酒で、アルコール度数がやや高く、コクや複雑さ、力強さが際立ちます。雑味や濃厚な味わいを楽しみたい方には個性的な選択肢です。
同じ銘柄でも、搾り方によってこれほど違いが出るのは日本酒ならではの魅力です。ラベルに「あらばしり」「中取り」「責め」と記載がある場合は、ぜひ飲み比べて自分好みの味わいを見つけてみてください6。飲み比べを通じて、日本酒の新しい楽しみ方が広がります。
12. よくある質問Q&A
Q1. 「中取り」とはどんな意味ですか?
中取りは、日本酒の搾り工程の中間部分で得られるお酒を指します。搾りの最初が「あらばしり」、最後が「責め」と呼ばれ、その中間が「中取り」です。雑味が少なく、香味のバランスが良いのが特徴です。
Q2. 「中取り」「中垂れ」「中汲み」は同じもの?
はい、これらはほぼ同じ意味で使われることが多いです。蔵元や地域によって呼び名が異なりますが、いずれも搾りの中間部分を指します。
Q3. 「中取り」の日本酒はなぜ人気なの?
中取りは雑味が少なく、香りと味のバランスが非常に良いため、品評会用や贈答用など特別な日本酒に多く使われています。見た目も透明感があり、飲みやすさが魅力です。
Q4. 「中取り」はどんな料理と合いますか?
中取りの日本酒は上品でまろやかな味わいなので、和食はもちろん、洋食や中華にもよく合います。特に天ぷらや白身魚、チーズなどと相性が良いです。
Q5. 「中取り」を選ぶときのポイントは?
ラベルに「中取り」「中垂れ」「中汲み」と記載があるかを確認しましょう。吟醸酒や純米大吟醸など、香り高いタイプに多いので、自分の好みに合わせて選ぶのがおすすめです。
Q6. 開封後はどれくらいで飲み切るべき?
開封後はできるだけ早めに、1週間以内を目安に飲み切るのが理想です。冷蔵庫で保存し、風味や香りが落ちないうちに楽しみましょう。
Q7. 「中取り」と他の搾り方の違いを楽しむには?
同じ銘柄で「あらばしり」「中取り」「責め」と飲み比べることで、搾り方による味や香りの違いを体感できます。日本酒の奥深さを知る良い機会になります。
中取りの日本酒は、知れば知るほど楽しみが広がります。疑問があれば、蔵元や販売店に気軽に質問してみてください。
まとめ
「中取り」は、日本酒の搾り工程において最もバランスが良く、雑味が少ない“おいしい部分”として多くの蔵元や日本酒ファンから高く評価されています。この中取りは、あらばしりのフレッシュさや責めの力強さとは異なり、透明感があり、香りと味わいの調和がとれた落ち着いたまろやかさが魅力です。
ラベルや説明文で「中取り」「中垂れ」「中汲み」などの表記を見かけたら、それは蔵元が自信を持って送り出す、品質の高い部分を瓶詰めした証です。ぜひ一度、そのクリアで上品な味わいを体験してみてください。あらばしりや責めと飲み比べることで、日本酒の奥深さや蔵ごとの個性もより感じられ、選ぶ楽しみが広がります。
日本酒選びの新たな基準として「中取り」を知っておくことで、より豊かな日本酒ライフが待っています。自分好みの一杯に出会うきっかけとして、ぜひ「中取り」の魅力を味わってみてください。