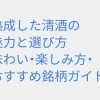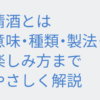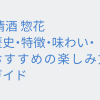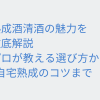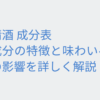平安時代 清酒|宮廷から僧坊酒へ―清酒誕生の歴史と技術革新
日本酒の歴史を語るうえで、平安時代は大きな転換期となりました。この時代、清酒(せいしゅ)の原型が生まれ、宮廷や寺院を中心に酒造技術が大きく発展します。現代の日本酒のルーツをたどりながら、平安時代における清酒の誕生や特徴、当時の社会背景や技術革新について詳しく解説します。お酒好きの方や歴史に興味のある方に、清酒の奥深い世界をやさしくご案内します。
1. 平安時代の酒造りの背景
平安時代(8世紀~12世紀)は、日本の宮廷文化が大きく花開いた時代であり、酒造りも大きく発展しました。この時代、宮中には「造酒司(みきのつかさ)」という酒造り専門の役所が設けられ、天皇や貴族のためにさまざまな種類の酒が造られていました。『延喜式』(927年)には、造酒司の役割や酒造りの詳細な手順、酒の種類や仕込み配合などが細かく記載されており、当時の高い技術力がうかがえます。
平安時代の酒は、現代のような透明な清酒だけでなく、米粒が残る濁酒(どぶろく)や、甘味の強い酒など多様でした。これらの酒は、神事や宮中の宴、季節ごとの行事など、さまざまな場面で欠かせない存在となっていました。特に貴族社会では、酒は社交や文化活動の中心にあり、和歌や物語にも頻繁に登場しています。
また、この時代の酒造りは、麹や乳酸菌を活用した高度な発酵技術がすでに使われており、日本酒の技術革新期ともいえる重要な時代でした。やがて酒造りは宮中から寺院や庶民へと広がり、後の日本酒文化の礎が築かれていきます。
平安時代の酒造りは、単なる飲み物の枠を超え、文化や人々の暮らしに深く根付いた存在だったのです。
2. 宮廷の造酒司と行事用の酒
平安時代の宮廷には、「造酒司(みきのつかさ)」という酒造専門の官職が設けられていました。造酒司は、律令制に基づく中央政府のもとで、酒の製造や管理、供給の全てを担う重要な役割を果たしていました1。単に酒を造るだけでなく、酒の品質や供給量を統制し、特に国家的な行事や宗教的儀式に欠かせない酒を準備することが主な任務でした。
造酒司が製造した酒は、天皇や貴族の宴、神事、祭事など、宮廷や神社での特別な場面で用いられていました。これらの酒は、現代の清酒とは異なり、米粒が残る濁酒や甘味の強い酒が中心でしたが、当時の高度な発酵技術や麹・乳酸菌の活用がすでに見られます。
また、造酒司は酒の品質管理も徹底して行い、材料や製造方法、保存状態などにも細かく気を配っていました。実際の酒造りは、都のある大和やその周辺の「酒戸(さかへ・さけこ)」と呼ばれる専門集団が担い、これが後の杜氏集団の起源とも言われています。
さらに、造酒司の活動を支えた水源として「造酒司井戸」と呼ばれる遺跡も発見されており、当時の酒造りがいかに組織的かつ緻密に行われていたかがうかがえます。
このように、造酒司は宮廷文化を支えるだけでなく、日本酒の技術発展や酒文化の礎を築いた存在でした。平安時代の酒造りは、単なる飲み物の製造にとどまらず、国家や神事、文化の中核を担う重要な役割を果たしていたのです。
3. 清酒の定義と当時の呼び名
平安時代における「清酒」とは、現代の日本酒に近い“澄んだ酒”を指していましたが、当時は「すみさけ」や「すみざけ」とも呼ばれていました。この呼び名は、「澄む(すむ)」という言葉から来ており、濁りの少ない、ろ過された酒を意味しています。実際、奈良時代から平安時代にかけての文献や木簡には「清酒(すみさけ)」や「浄酒(すみざけ)」といった表現が登場し、当時から澄んだ酒が特別視されていたことがわかります。
平安時代の清酒は、主に宮中の祭事や神事、特別な宴席などで用いられました。国家や神への奉納、重要な儀式の際に使われることが多く、一般庶民が日常的に口にできるものではありませんでした。『延喜式』などの法典にも、清酒の製造や用途、品質管理について細かく記載されており、国家的に管理された貴重な酒だったことがうかがえます。
また、当時の清酒は、濾過の技術が今ほど発達していなかったため、現代の透明な日本酒とは異なり、やや黄金色がかった澄んだ酒だったと考えられています。それでも、濁酒(どぶろく)などと比べると格段に澄んでおり、祭事や特別な用途にふさわしい“上等な酒”として重宝されていました。
このように、平安時代の「清酒(すみさけ)」は、祭事や特別な場で用いられる貴重な存在であり、当時の酒文化や社会のあり方を象徴するものでした。
4. 平安時代の酒の種類と特徴
平安時代には、現代以上に多様な種類の酒が造られていました。その背景には、宮廷文化の発展とともに、国家が酒造りを厳密に管理し、儀式や行事に合わせたさまざまな酒が必要とされたことがあります。927年に完成した『延喜式』には、当時の酒造りの詳細な技法や分類が記録されており、13種類もの酒の製法が記されています。
代表的なものとしては、冬に仕込み何度も搾ることで酸味が少なく甘口の澄み酒「御酒(ごしゅ)」、初秋に仕込む濃厚甘口の「御井酒(ごいしゅ)」、酒を汲水代わりに使う甘い「醴酒(れいしゅ)」、麦芽や米麹を使った味醂系の「三種糟(さんしゅそう)」、さらに新嘗祭などに用いられる「白酒(しろき)」や、灰を加えて色を付けた「黒酒(くろき)」などがありました。
これらの酒は、米や麹、水の配合や仕込み方法、発酵の度合いなどによって味わいや用途が大きく異なっていました。たとえば、白酒や黒酒は大きな篩(ふるい)で濾過されるなど、当時としては高度な濾過技術も使われていたことが分かります。
また、甘味の強い酒や濁り酒、現代の味醂や甘酒の原型となるような酒も造られており、用途も祭事用、神事用、貴族の宴席用など多岐にわたっていました。このように、平安時代の酒は味や製法のバリエーションが豊かで、現代の日本酒文化の基礎を築いた時代だったと言えるでしょう。
5. 僧坊酒の登場と技術革新
平安時代の後半になると、酒造りの中心は宮廷の造酒司から寺院へと移り、各地の大寺院で造られる「僧坊酒(そうぼうしゅ)」が盛んになりました。僧坊酒とは、寺院の僧侶たちが自らの財源確保や祭事のために醸造したお酒のことです。寺院は広大な荘園や豊富な資源を持ち、また知識人が集まる場でもあったため、酒造技術の研究・発展が加速しました。
この時代、僧坊酒によって酒造りの技術は飛躍的に発展しました。たとえば、麹・蒸米・水を段階的に仕込む「段掛け法」や、現在の生酛造りの原型となる技術が生まれています。奈良の正暦寺で造られた「菩提泉(ぼだいせん)」は、特に高い評価を受け、後の日本酒造りにも大きな影響を与えました。
また、寺院での酒造りは、単なる自家消費や祭事用にとどまらず、やがて販売も行われるようになり、寺院の財政基盤を支える重要な産業となりました。僧坊酒の品質は非常に高く、時の権力者や武将たちにも愛され、寺院はその財力と技術力で大きな影響力を持つようになりました。
僧坊酒の登場は、酒造技術の革新をもたらし、濾過や火入れ、段仕込みなど、現代にも通じる多くの技術がこの時代に発展しました。こうして平安時代から中世にかけて、僧坊酒は日本酒文化の発展を大きく牽引したのです。
6. 清酒製法の原型と「菩提泉」
平安時代から続く日本酒造りの歴史の中で、奈良の正暦寺で生まれた「菩提泉(ぼだいせん)」は、現代清酒の原型とされる重要なお酒です。正暦寺は、室町時代に「菩提酛(ぼだいもと)」という独自の酒母造りの技法を確立し、これによって雑菌の繁殖を防ぎ、安定した発酵を実現しました。この菩提酛を用いた「菩提泉」は、乳酸発酵を活かした酒母づくりが特徴で、寺の湧水と生米を使い、2日間かけて乳酸発酵させた「そやし水」を仕込み水に使うことで、健全な酵母の育成を可能にしました。
この技術革新により、冬だけでなく夏季でも安定した酒造りができるようになり、現代の清酒に通じる透明感や上品な味わいが生まれたとされています。また、正暦寺の酒造りでは、掛米と麹米の両方に白米を使う「諸白(もろはく)」製法も登場し、これが後の高級酒の主流となりました。
「菩提泉」は、当時から質の高い酒として知られ、戦国武将や貴族にも愛されていました。現在も奈良県内の蔵元が協力して「菩提酛」を復活させ、伝統的な清酒造りを守り続けています。
このように「菩提泉」は、乳酸発酵や諸白仕込みなど、現代の清酒製法の原点となる技術を数多く生み出し、日本酒の品質向上と多様化に大きく貢献しました。正暦寺で生まれたこの伝統の味を知ることで、清酒の奥深い歴史や技術の進化をより身近に感じていただけるはずです。
7. 濾過技術と清酒の透明度
平安時代の酒造りでは、酒の透明度を高めるための濾過技術がすでに用いられていました。当時は現代のような精密なフィルターはありませんでしたが、布や炭、砂などを使った原始的な濾過方法が工夫されていました。これらの素材を使い、発酵を終えたもろみから米粒や酵母の残りを取り除くことで、濁りを減らし、より澄んだ酒を得ることができたのです。
『延喜式』などの古文書には、酒の種類ごとに大篩(おおふるい)や筌(うけ)といった道具を使って濾過を行っていた記録が残っています。この工程により、当時の清酒は現代ほど透明ではないものの、濁酒(どぶろく)よりも明らかに澄んだ見た目と味わいを持っていたと考えられます。特に、諸白(もろはく)などの高級酒は、濾過によって雑味が少なく、透明感のある仕上がりが評価されていました。
また、奈良の正暦寺などの寺院では、木炭を使った濾過や、段階的な仕込みと組み合わせることで、酒の品質と安全性を高める技術革新も進みました。こうした濾過技術の発展は、やがて現代の清酒につながる透明感のある日本酒の誕生に大きく寄与したのです。
このように、平安時代の酒造りでは、限られた技術の中でも工夫を凝らし、より美しく澄んだ酒を目指して努力が重ねられていました。濾過技術の進化は、清酒の価値を高め、特別な場で振る舞われる上等な酒としての地位を確立する要因となったのです。
8. 清酒の流通と消費層
平安時代の清酒は、その生産量が非常に限られていたため、流通範囲もごく狭いものでした。主に宮廷や有力な貴族、そして大寺院といった特別な階層のみが清酒を楽しむことができたと考えられています。当時の酒造りは、朝廷直属の酒造組織「造酒司(さけのつかさ)」や、後に発展した寺院の僧坊酒が中心となっていました。特に奈良の正暦寺をはじめとする寺院で造られた僧坊酒は、その品質の高さから「南都諸白」として名声を博し、高級酒として扱われていました。
この時代の清酒は、まだ今日のような完全な透明度やすっきりした味わいではなく、玄米の糠が残る黄金色がかった濃厚な酒が多かったとされています。それでも、僧坊酒の技術革新によって三段仕込みや乳酸菌発酵、火入れ殺菌、木炭濾過といった現代にも通じる技法が生まれ、上品な味わいの諸白(もろはく)などが人気を集めるようになりました。
一方、庶民の間では自家製の濁り酒(どぶろく)が主流であり、清酒はまだまだ高嶺の花でした。平安時代の清酒は、特別な場や人のための贅沢品であり、社会的地位や財力を象徴する存在でもあったのです。
このように、平安時代の清酒は流通量も消費層も限られていましたが、僧坊酒の発展を通じて酒造技術が大きく進化し、やがて武家や町人階層へと広がっていく基礎を築きました。清酒が一般庶民のものとなるのは、さらに時代が下ってからのことになります。
9. 清酒と祭事・儀式の関係
平安時代の清酒は、単なる嗜好品ではなく、神事や宮中行事など特別な場で用いられる、極めて神聖な存在でした。古くから日本酒は「お神酒(おみき)」として神様に供えられ、神聖な儀式やお清めの場で欠かせない役割を果たしてきました。神前に供えられた酒には霊力が宿るとされ、儀式の後に人々がその酒をいただくことで、神様のご加護や恩恵を受けると信じられていました。
平安時代の国家的な祭祀や宮中行事では、清酒をはじめとするさまざまな酒が用意され、厳粛な手順で神々や祖先に捧げられました。たとえば『延喜式』には、清酒が「神に捧げる神聖な供物」として扱われていた記述があり、造酒司(さけのつかさ)という役所が厳密な製法と品質管理のもとで祭祀用の酒を製造していました。また、地鎮祭や新年の屠蘇(とそ)など、土地や人を清める儀式にも日本酒は欠かせませんでした。
さらに、平安貴族の生活でも、春の「花宴」や秋の「月見酒」、節目ごとの「御酒の儀式」など、季節や行事に合わせて日本酒が振る舞われ、人々の心をつなぐ社交の潤滑油となっていました。和歌や物語にも酒宴の場面が多く登場し、酒は恋や季節の風情を彩る文化的なアイテムでもありました。
このように、平安時代の清酒は、神聖さや清めの力をもつ特別な酒として、神事・儀式・社交の場で重要な役割を担っていました。現代でも日本酒が祝い事や神事で使われる背景には、こうした長い歴史と深い信仰が息づいているのです。
10. 平安時代の清酒と現代清酒の違い
平安時代の清酒と現代の清酒には、製法や味わいに大きな違いがあります。まず、平安時代の清酒は、現代のように精米技術や温度管理が発達していなかったため、米の外側のぬか分が多く残り、酒の色もやや黄金色がかっていました。また、発酵のコントロールも難しく、アルコール度数は低めで、発酵しきれなかった糖分が多く残るため、甘く濃厚な味わいが主流だったと考えられます。
この時代の清酒は、主に宮廷や寺院など限られた場で特別な儀式や祭事に用いられ、製法も多様でした。『延喜式』には十数種類もの酒造法が記されており、現代のような透明度の高い清酒はまだ一般的ではありませんでした。濾過も布や炭などを使った原始的な方法で行われていたため、現代の清酒ほどクリアな見た目やすっきりした口当たりではなかったのです。
現代の清酒の基礎が確立したのは、室町時代以降です。精米技術の進歩や乳酸菌を使った酒母造り、段仕込み、火入れ殺菌、木炭濾過などの技術が発展し、安定して品質の高い、透明度のある清酒が量産できるようになりました。また、現代では温度管理や衛生管理も徹底され、辛口や淡麗など多様な味わいが楽しめるようになっています。
このように、平安時代の清酒は現代のものとは異なる独自の個性を持っていましたが、時代を経て技術が進化したことで、私たちが親しむ現代清酒が誕生したのです。古代の酒文化を知ることで、現代の日本酒の奥深さや多様性にも、より興味が湧いてくるのではないでしょうか。
11. 清酒製造技術の発展とその後
平安時代に確立された酒造りの技術は、後の時代に大きな発展を遂げ、現代の日本酒文化の礎となりました。平安時代には、宮廷の造酒司や寺院の僧坊酒によって、麹菌を使った発酵や、蒸米・麹・水を段階的に仕込む「段掛け法」など、基礎的な酒造技術が体系化されていきました。この時代の知識や技術は、やがて寺院や酒屋に広がり、酒造りがより広範に行われるようになります。
室町時代に入ると、寺院や都市部の酒屋が酒造りの中心となり、「火入れ殺菌法」や「三段掛け法」、「菩提酛」など、現代にも通じる技術革新が相次ぎました。また、酒母の育成や白米の使用、上槽法(搾りの技術)なども発展し、品質の安定した清酒が生まれる土台が築かれます。
江戸時代には、さらに技術が洗練され、現在の日本酒とほぼ同じ製造方法が確立されました。杜氏や蔵人といった専門職集団が生まれ、冬期に集中して酒造りを行う「寒造り」や、低温加熱による保存・熟成技術も普及します。こうした長い歴史の中で、日本酒は庶民にも広く親しまれるようになり、地域ごとの個性豊かな地酒文化も発展しました。
このように、平安時代に培われた酒造技術は、室町・江戸時代の革新を経て、現代の多様で高品質な日本酒文化へとつながっています。長い年月をかけて積み重ねられた知恵と工夫が、今もなお日本酒の美味しさと奥深さを支えているのです。
まとめ:平安時代清酒の意義と現代へのつながり
平安時代は、日本酒――特に清酒――の誕生と酒造技術の発展において、とても重要な時代でした。この時代、宮廷や神社の儀式、貴族の宴席などで清酒が文化の中心的な役割を担い、国家の管理のもとで厳格に製造・品質管理されていました。また、法典『延喜式』には酒造りの詳細な技法や用途が記録されており、当時から清酒が神聖な供物や祭祀の必需品として扱われていたことがわかります。
やがて、宮廷中心の酒造りは寺院へと広がり、「僧坊酒」と呼ばれる寺院酒が高い評価を受けるようになります。奈良の正暦寺で生まれた「諸白造り」などの技術革新は、室町時代以降の日本酒造りの基礎となり、現代の清酒へと受け継がれていきました。
こうした歴史を知ることで、日本酒が単なる嗜好品ではなく、神事や文化、そして人々の暮らしと深く結びついてきたことが実感できるはずです。平安時代の清酒の物語を知ることは、現代日本酒の奥深さや伝統への興味をさらに広げてくれます。ぜひ、歴史の一杯にも思いを馳せながら、今の日本酒を味わってみてください。